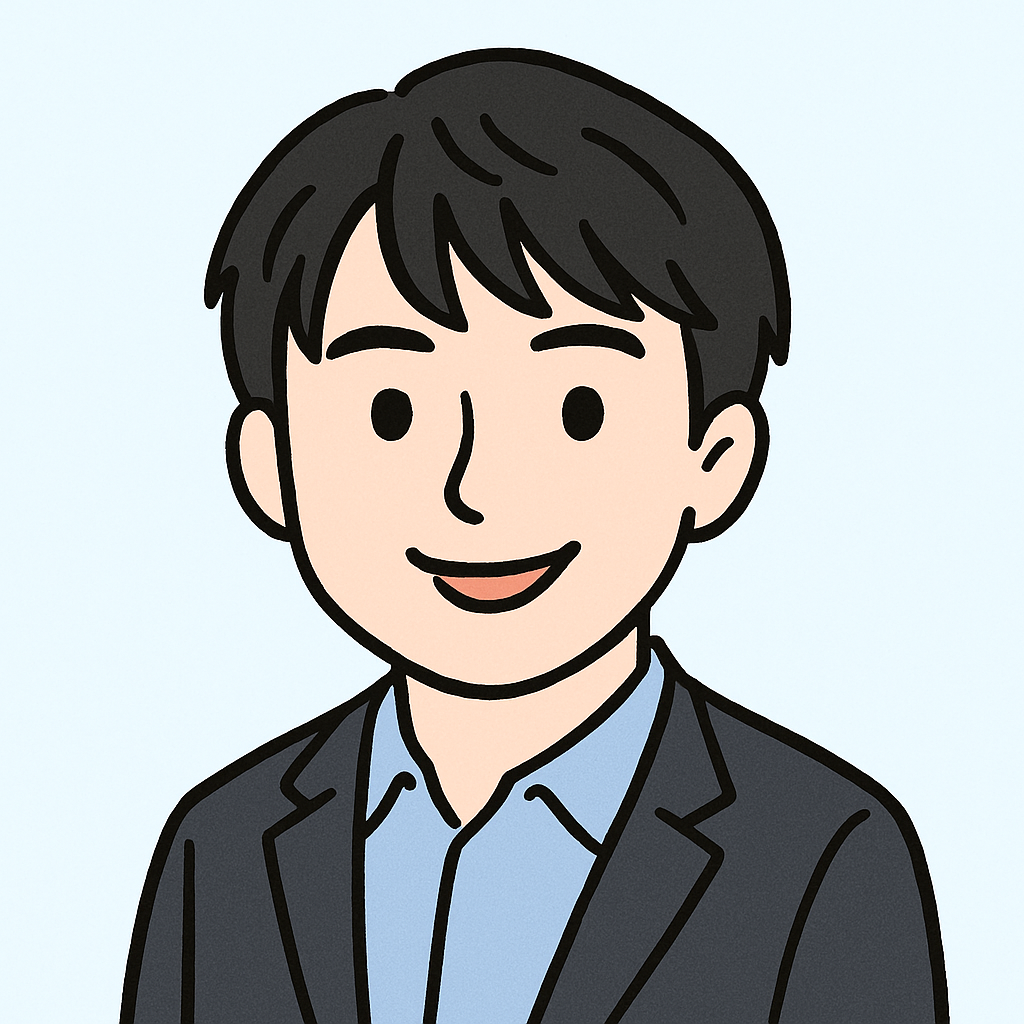こんにちは!「うちの社員は年齢が高くてITに詳しくない…」「自分自身がデジタルに苦手意識がある」「若い企業に置いていかれるのではないか」そんな悩みをお持ちではありませんか?
実は、年齢は決してデジタル化の障壁ではないんです!本記事では、平均年齢55歳の会社がITを活用して業績を大幅アップさせた実例と、59歳の社長が語る「今からでも遅くない」納得の理由をご紹介します。自分たちには無理だと思い込んでいた方も、この記事を読めば「うちでもできるかも」と感じていただけるはずです。
この記事を読むことで、あなたは以下のことがわかるようになります。
- 年齢層が高い会社がデジタル化に成功した具体的な方法
- ベテラン社員がITを活用して活躍するようになった変化のプロセス
- デジタル化に踏み出すための「小さな一歩」の見つけ方
- ITに詳しくない経営者が実践した成功のポイント
- 経験豊富な人材だからこそできるデジタル活用法
「うちには無理」を覆した転機
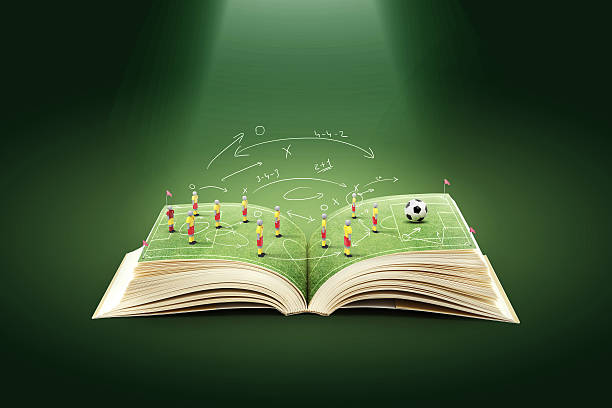
コロナ禍がもたらした危機感
佐藤電機工業(仮名)は創業45年、従業員30名の町工場。平均年齢は55歳、最年少でも38歳という「若手不在」の会社でした。2020年、コロナ禍で対面営業が困難になり、受注が急減。社長の佐藤さん(当時59歳)は大きな危機感を抱きます。
「このままでは会社が立ち行かなくなる…でも、私自身もITに詳しくない。社員の多くもデジタルに抵抗がある。何から始めればいいのか…」
多くの経営者が抱えるこの悩み。しかし佐藤社長が取った行動は、意外にもシンプルなものでした。
「年齢」は言い訳にならない理由
佐藤社長がまず気づいたのは、「年齢はデジタル化の障壁ではない」という事実でした。
「よく考えてみると、私たちの世代(1960年代生まれ)は、大学時代にコンピュータに触れる機会があった世代です。社会人になってからPC-9800シリーズなどの登場を経験し、自然とITリテラシーが養われてきました」と佐藤社長は振り返ります。
実は、日本の経営者の平均年齢は60.5歳。多くの企業が同様の課題に直面しているのです。しかし、アメリカにおける高齢者の起業成功率は70%を超えており(若者は28%)、長年の経験や知識を活かせる世代だからこそ、新しい挑戦も成功しやすいのです。
小さな一歩から始めた成功体験

弁当注文アプリからのスタート
佐藤社長がまず取り組んだのは、全社的な大規模システム導入ではありませんでした。社内で最も不満の声が大きかった「弁当注文」という小さな業務から変革をスタートさせたのです。
毎日、総務担当者が各部署を回って弁当注文を聞いて回り、FAXで発注する—。この非効率な作業を、簡単なスマホアプリでデジタル化しました。
ある社員の反応:「最初は『またわけのわからないものを導入して…』と思いました。でも使ってみたら驚くほど簡単で、しかも時間が節約できる。これならやってみる価値があるなと感じました」(製造部・山田さん(61歳))
「できること」を少しずつ増やす
弁当注文アプリという小さな成功体験から、社内のデジタル化は徐々に広がっていきました。
次に取り組んだのは「情報共有」:
- 社内掲示板をオンライン化
- 業務マニュアルをデジタル文書化
- 会議資料のペーパーレス化
「若い人たちなら一度で覚えられることも、私たちは何度も繰り返し練習しました。でも、できることが一つずつ増えていくのが楽しくなってきたんです」(営業部・鈴木さん(58歳))
ベテラン社員の変化と成長

「ITが苦手」という思い込みからの脱却
「当初、多くのベテラン社員が『自分はITが苦手だから』と消極的でした。しかし、実際に使ってみると『思ったより簡単だ』と驚く声が多かったのです」と佐藤社長は振り返ります。
実は、調査によればシニア世代のデジタル化への期待は年齢によって異なり、特に高齢男性ほど「期待する」割合が高い傾向があるのです。佐藤電機工業でも同様の傾向が見られ、むしろ50代後半から60代の社員の方が積極的に取り組む姿勢を見せました。
ベテランだからこそできること
デジタル化の取り組みを通じて、ベテラン社員の価値が再発見されました。
ある製造部門のベテラン社員の例: 60歳のベテラン職人・高橋さんは、タブレットを使って自分の技術をデジタル記録することにチャレンジ。若手への技術伝承が大きな課題だった同社にとって、これは革命的な変化でした。「自分の技術が残せるなら」と、最初は気が進まなかったタブレット操作も熱心に学びました。
結果として作成された「高橋メソッド」は、新人研修に大活躍。「若手に直接教えるときより、むしろ理解が早くなった」と高橋さんは驚きます。
デジタル化による具体的な成果

業務効率の劇的向上
佐藤電機工業では、段階的なデジタル化により、様々な業務が効率化されました。
具体的な改善例:
- 生産管理システム導入:月間200時間の作業削減
- オンライン商談ツール活用:移動時間削減で商談件数1.5倍に
- クラウド会計システム:請求書処理時間が1/3に
「以前は担当者が休むと業務が滞っていましたが、今はシステムで情報が共有されているので、誰でもカバーできるようになりました」(総務部長・木村さん(63歳))
売上・利益の大幅増加
デジタル化の最大の成果は、業務効率化を超えた売上・利益への貢献です。
佐藤電機工業の場合:
- オンライン商談の導入で地理的制約がなくなり、全国からの受注が増加
- デジタルカタログとオンライン見積システムで成約率アップ
- データ分析による製品改良で既存顧客からのリピート注文増加
「2年間で売上が約2倍になりました。正直、私自身が一番驚いています」と佐藤社長は語ります。
ITに詳しくない経営者が実践したこと

自らが率先して学ぶ姿勢
「私自身がまず使ってみることを心がけました。社長である私が使えないものを社員に使えというのは説得力がありません。最初は苦労しましたが、分からないことは若手社員に聞くなど、謙虚な姿勢で取り組みました」
実際、近年では「社長=IT音痴」という構図は急速に変化しており、特に1959年前後に生まれた経営者は、学生時代や社会人初期にコンピュータやパソコンの普及を経験しており、ITリテラシーが比較的高い傾向があります。
外部の知見の活用
ITに詳しくない経営者が成功するためには、外部の知見を上手く活用することも重要です。佐藤電機工業では、以下の方法で外部知見を活用しました:
- 地域の商工会議所が開催するIT活用セミナーに参加
- 地元のIT企業と連携し、定期的にアドバイスを受ける体制を構築
- 取引先の銀行が提供するデジタル化支援プログラムを活用
「分からないことは恥ずかしがらずに聞く」という姿勢が、スムーズなデジタル化を支えました。
過去の成功体験への固執を捨てる
経営者が陥りがちな罠の一つが「過去の成功体験への固執」です。特に長年経営してきた企業では、過去に成功した経験があると、それにとらわれて考え方の柔軟性を失ってしまうことがあります。
佐藤社長は「今までのやり方が通用しない時代になった」と認識し、過去の成功体験に固執せず新しい技術や方法を積極的に取り入れました。
「最初は『こんなやり方で本当に大丈夫か』と不安でした。でも、実際にやってみると、予想以上の効果があったんです。年を取ると新しいことへの抵抗感が強くなりますが、その壁を乗り越えると、また新しい景色が見えてきます」
成功のための3つのポイント

1. 現場の声を大切にする
佐藤電機工業のデジタル化成功の大きな要因は、トップダウンではなく現場の声を大切にしたことでした。
「紙の作業指示書が風で飛んでしまう」「写真と報告書の紐づけに時間がかかる」という現場の声から、タブレットを活用した業務システムを開発。このシステムは現場社員自身が仕様を考案し、IT部門と協働で改良を重ねたことで、導入後の業務効率が約150%向上しました。
実践方法:
- 匿名で意見を集められるデジタル提案箱の設置
- 定期的な「業務改善ミーティング」の開催
- 「困りごと」を気軽に共有できる雰囲気づくり
2. ベテラン社員と若手社員の協働
デジタル化の推進には、ベテラン社員の業務知識と若手社員のデジタルスキルを組み合わせることが効果的です。佐藤電機工業では、若手とベテランがペアになって新しいシステムの導入や改善に取り組む「バディ制度」を導入しました。
「若手はITに強く、ベテランは業務に詳しい。この組み合わせが非常に効果的でした。お互いが教え合うことで、世代間のコミュニケーションも活性化しました」と佐藤社長は語ります。
3. 継続的な学習環境の整備
「学びに年齢は関係ない」という考えのもと、佐藤電機工業では社内に継続的な学習環境を整備しました。
具体的な取り組み:
- 週に一度の「デジタルランチ」:社員が交代でデジタルツールの使い方や活用事例を紹介
- 「失敗してもOK」という文化の醸成:新しいことにチャレンジする姿勢を評価
- オンライン学習プラットフォームの導入:自分のペースで学べる環境の提供
「最初は『もう歳だから新しいことを覚えるのは難しい』と言っていた社員も、少しずつできることが増えていくと自信がつき、むしろ積極的に新しいツールを試すようになりました」(総務部長・木村さん)
失敗しないための注意点

成功事例から学ぶだけでなく、失敗例からも大切な教訓が得られます。佐藤電機工業も試行錯誤の過程でいくつかの失敗を経験しました。
無理な全社一斉導入は避ける
ある大手企業では、現場の準備が整わないまま全社一斉にシステムを導入した結果、混乱が生じて結局元の方法に戻したという失敗例があります。
佐藤電機工業では、まず一つの部署で試験的に導入し、問題点を洗い出してから他部署に展開するというアプローチを取りました。
目的を明確にする
DX推進に失敗した企業の事例から学べる重要な点として、具体的な達成目標を示さずに投資を行うことの危険性があります。
「何のためにデジタル化するのか」を常に問い続け、単なる「流行りだから」ではなく、明確な業務改善や顧客価値向上につながる取り組みに注力しました。
現場の声の取り入れ方
DX推進のよくある失敗の一つに、現場の意見を聞きすぎることがあります。ある大手企業では、現場の意見を全て取り入れて現状の業務をデジタル化した結果、高度で複雑なシステムができあがり、かえって使いづらくなったという事例があります。
佐藤電機工業では、現場の声を聞きながらも、「本当に必要な機能は何か」を常に検討し、シンプルで使いやすいシステムづくりを心がけました。
まとめ:デジタル変革は「今からでも遅くない」

59歳の佐藤社長は最後にこう語ります。
「デジタル化は目的ではなく手段です。大切なのは、お客様により良いサービスを提供し、社員がより働きやすい環境を作ることです。その手段としてデジタル技術を活用するのであれば、今からでも決して遅くはありません。むしろ、長年の経験とデジタル技術を組み合わせることで、若い企業にはない強みを発揮できるのです」
平均年齢55歳の会社がITで業績アップを実現した事例は、年齢を言い訳にせず、小さな一歩から始めることの重要性を教えてくれます。デジタル化への道のりは決して平坦ではありませんが、経営者の強いリーダーシップと社員の積極的な参加があれば、どのような企業でも成功への道を切り開くことができるのです。
「若い企業だけがデジタルで成功できる」という思い込みを捨て、ぜひあなたの会社でも最初の一歩を踏み出してみてください。
ビジネスパートナーからのメッセージ
まずは15分間のヒアリングで貴社の現状と課題をじっくりお聞きします。その後、専門アドバイザーが45分間かけて、貴社の業務に最適なデジタル活用法を具体的にご提案。明日から実践できる具体的な導入ステップまで、わかりやすくお伝えします。
まずは無料の個別セミナーで、貴社のデジタル変革への第一歩を踏み出してみませんか?
デジタル活用は、準備さえしっかりすれば、明日からでも始められます。ぜひ一歩踏み出してみてください!